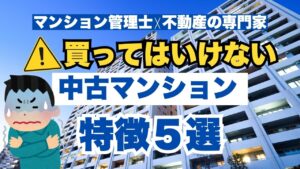【稲沢市】買ってはいけないマンション5選|管理士が警告

こんにちは、稲沢あんしん不動産の佐藤です。
今日は私の経験をもとに「いつの時代でも売れにくいマンションの特徴5選」についてお話しします。これを知っておけば、対策も立てられますよ。
私は不動産売買の仲介をしながらマンション管理士として実際に分譲マンションの管理コンサルティングをしています。
その経験から「このマンションは買わない方がいいな」と感じる特徴をお伝えします。
外観や立地だけでは分からない、管理面の内部事情から見た「避けるべきマンション」の特徴です。
分譲マンションの管理も分かっている不動産会社ならではの視点として、ご参考にしていただければ幸いです。
- マンション管理士が警告する買ってはいけない5つの特徴
- 長期修繕計画がないマンションのリスク
- 管理費3万円超のマンションが抱える問題
- 理事会の役員固定化が招くトラブル
- 稲沢市でマンション購入前にチェックすべきポイント
マンション購入で失敗しないために、外観や立地だけでなく管理面の内部事情も重要です。マンション管理士として5000件以上の査定と管理コンサルティング経験から、本当に注意すべきポイントをお伝えします。
中古マンション選びの基本は失敗しない中古マンション探し|内見前に8割の勝負が決まる5つのステップで詳しく解説しています。
結論:私が買ってはいけないと注意するマンションの5つの特徴

まず結論からお伝えします。私が「このマンションは購入を躊躇する」と思う5つの特徴は
- 長期修繕計画がない
- 管理費・修繕積立金の合計が毎月3万円以上
- 理事会の役員が固定化されている
- 戸数が極端に少ない
- 特定の管理会社が入っているマンション
これらの特徴があるマンションは、将来的な資産価値や住み心地に大きな影響を与える可能性があります。では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
特徴1:長期修繕計画がないマンション

1つ目は「長期修繕計画がないマンション」です。これは 絶対に避けたい 重大なリスク要因です。
マンションの維持修繕は長期修繕計画があってこそ成り立ちます。大規模修繕工事は一般的に13〜17年に1回行われますが、それに合わせて修繕積立金を計画的に貯めていく必要があります。
計画がないということは、工事の時期が来ても実施できるかどうか不明です。
実際に私がコンサルティングを行っているマンションでも、大規模修繕工事の時期なのにお金がないというケースに対応しています。
お金がなければ、次の2つの選択肢しかありません:
- 管理組合が金融機関から借り入れをする
- 区分所有者から一時金(数十万円〜百万円規模)を集める
どちらも住民にとって大きな負担となります。
また、大規模修繕工事の前にも設備の故障や交換が必要になることもあります。
例えばエレベーターのリニューアルなどは1000万円単位の費用がかかります。
長期修繕計画がない場合は、将来が不安しかないので購入は注意するべきです。
もちろん、現在の積立金額と将来の予測から判断することもできますが、多くの場合は資金が不足する可能性が高いでしょう。
中古マンション購入時は、必ず長期修繕計画と修繕履歴を確認しましょう。内見時のチェックポイントは中古マンション内見で失敗しない完全ガイドをご覧ください。
大規模修繕についてはマンション大規模修繕の談合問題を完全解説も参考にしてください。
特徴2:管理費・修繕積立金の合計が毎月3万円以上

2つ目は「管理費と修繕積立金の合計が毎月3万円以上」のマンションです。
これは毎月の負担が大きく、将来的に売却する際も不利になります。
購入を検討する人の多くは、月々の管理費・修繕積立金の金額を重視するからです。
さらに重要なのは、管理費・修繕積立金の値上げは「片道切符」だということです。
専門家のコンサルティングが入らない限り、下がることはほとんどありません。
管理会社は上げる方向でしか提案しないことが多いのが現実です。
築年数が経つほど修繕する箇所も増え、出費も増加します。
3万円を超えているマンションはもちろん、3万円に近づいているマンションも注意が必要です。
もし既にマンションを所有していて売却を検討している場合はマンション売却の流れと注意点も参考にしてください。
特徴3:理事会の役員が固定化されている

3つ目は「理事会の役員が固定化されているマンション」です。
これは私の個人的な経験からですが、約7年前に分譲マンションのコンサルをするなら理事も経験すべきだと思い、理事を務めたことがあります。
そのマンションでは理事長と主要メンバーが10年以上固定化されていました。
驚いたのは、役員報酬が理事長一人に年間20万円ほど支払われていたことです。しかも管理規約に明記されておらず、マンションは修繕資金が不足していたんです。
私が「規約にも載っていないのはおかしいのでは」と指摘したところ、「数十年前に決まっていて、当時居住者には案内を回したので規約はないが有効」と言われました。
さらに、管理会社と密接な関係にあり、管理会社の提案以外は受け付けないという状況でした。
役員の固定化は、このように一部の人の意見だけで運営されるリスクがあります。
私は1年で理事を辞めましたが、管理の難しさを実感しました。
マンションを購入する際は、理事会の議事録を確認し、役員の入れ替わりがあるかどうかチェックすることをおすすめします。
また、総会の出席率や議決権行使書の提出率も、健全な管理組合かどうかを判断する重要な指標です。
2026年4月に施行される区分所有法改正については区分所有法改正を徹底解説|決議要件緩和でマンション居住が変わる3つのポイントをご覧ください。
特徴4:戸数が極端に少ないマンション

4つ目は「戸数が極端に少ないマンション」です。
戸数が30戸以下のマンションは、修繕積立金が十分に貯まりにくいという問題があります。 設備投資や人件費などの固定費は、30戸でも50戸でも変わらない部分が多いですから、戸数が多いほど1世帯あたりの負担は軽減されます。
例えば、エレベーター1基の交換費用が1200万円かかるとします。
- 20戸のマンションでは、1戸あたり60万円の負担
- 50戸のマンションでは、1戸あたり24万円の負担
このように、戸数が少ないと1戸あたりの負担が大きくなります。
また、戸数が少ないと役員の当番も頻繁に回ってきます。これは構造的な問題なので、避けられない課題です。理事は通常1〜2年の任期ですが、20戸のマンションでは4〜5年に1回は役員を務めることになります。
小規模マンションの魅力はプライバシーや静かな環境ですが、管理面では課題が多いことを理解しておきましょう。
稲沢市や一宮市など愛知県内でマンション購入を検討している方は稲沢市で失敗しない不動産購入|土地・戸建て・中古マンション選びも参考にしてください。
特徴5:対応が悪い管理会社が入っているマンション

5つ目は「対応の質がイマイチな管理会社が入っているマンション」です。
管理コンサルティングを行っている私は、自然と様々な管理会社の対応を比較する機会が多くあります。管理会社の質は本当にさまざまで、担当フロントマンの対応レベルも影響しますが、根本的には会社の方針や組織文化が重要な要素となります。
管理会社のフロントマンとは、マンション管理会社があなたのマンションの窓口となる担当者のことです。管理組合の運営をサポートしたり、建物の維持・管理などを担当する役割を担います。住民と管理会社の間に立ち、マンション管理に関する業務を幅広くサポートします。管理会社のフロント担当のレベルが管理組合の運営にも大きく影響するため、フロントマンの対応が十分でない場合は改善を要請することで、マンション全体の管理の質も向上する傾向があります。
一部の管理会社では、優秀な担当者もいる一方で、残念ながら期待に応えられない対応をする担当者の割合が高い傾向があります。
電話での応対が遅い、報告書の提出が遅れる、トラブル対応が後手に回るなど、様々な場面でそれが表れます。
こうした状況は個々の担当者の問題というより、会社のDNAみたいな感じですね。
実際、私自身の経験から、特定の管理会社が入っているマンションについては、購入を慎重に検討した方がよいケースがあります。長年のコンサルティング経験から、管理会社の対応の質が資産価値や住環境に与える影響は決して小さくないことを実感しています。
購入を検討している方へのアドバイスとして、内覧時に売主様へ管理会社の対応について率直に質問してみるのが良いでしょう。
また、可能であれば管理組合の方や現居住者から、
「管理会社の対応は迅速か」
「トラブル時の解決力はどうか」
といった具体的な点について聞くことができれば、より実態に即した判断ができます。
マンション購入時のプロの査定ポイントについてはマンション査定でプロがチェックするポイントをご覧ください。
マンション購入でよくある質問
- 中古マンション購入時に必ず確認すべき書類は何ですか?
-
長期修繕計画、修繕履歴、管理組合の議事録、管理規約は必ず確認しましょう。内見時のチェックポイントは中古マンション内見で失敗しない完全ガイドをご覧ください。
- 稲沢市でマンション購入する場合、どんなサポートがありますか?
-
稲沢あんしん不動産では、マンション管理士の視点も含めた物件選びのアドバイスを行っています。詳しくは稲沢市で失敗しない不動産購入をご覧ください。
- 購入したマンションを将来売却する場合、どんな準備が必要ですか?
-
マンション売却の流れと注意点についてはマンション売却の完全ガイドで詳しく解説しています。
- 管理費や修繕積立金が高いマンションは売却時に不利ですか?
-
はい、管理費3万円超のマンションは売却時に不利になる傾向があります。詳しくは売れにくいマンションの特徴5選と確実に売る方法をご覧ください。
まとめ

今回は、私の経験から「購入したら後で大変になるだろうな」と思うマンションの特徴をお話しました。
外観からは分からない、管理面の内部事情も含めた「買わないマンション」の特徴です。
外から見えない部分もあり、実際に中に入ってみないと分からないこともあります。
購入前には次の5点をチェックしましょう
- 長期修繕計画の有無と内容
- 管理費・修繕積立金の金額と上昇傾向
- 理事会の運営状況(議事録などで確認)
- マンションの戸数とコスト負担のバランス
- 管理会社の評判・対応の質
マンション購入は人生の大きな買い物です。外観や立地だけでなく、こうした「見えない部分」にも目を向けることで、将来的な後悔を避けることができます。
不安な点があれば、マンション管理士などの専門家に相談することも検討してみてください。
稲沢あんしん不動産では、マンション管理士としての視点も含めた物件選びのアドバイスをさせていただいています。
稲沢市でマンション購入をお考えの方へ
稲沢あんしん不動産では、マンション管理士の視点も含めた物件選びのアドバイスを無料で行っています。
- 長期修繕計画や管理組合の運営状況をプロの目でチェック
- 管理費・修繕積立金の適正額を判断
- 将来の資産価値を考慮した物件選び
- 稲沢市・一宮市エリアの物件情報を多数保有
28年の経験と5000件以上の査定実績、マンション管理士としての専門知識から、あなたに最適な物件選びをサポートします。